これまでに一般知識の文章理解の対策について記事にさせて頂きましたが(過去記事リンク先→①・②)
結構な反響があり、twitterのDMで、もう少し詳しく解説して欲しいというリクエストを頂きました。
ということで、文章理解の対策シリーズ③になります!
令和3年度、問58の引用図書を借りてきたぞ♪
おそらくですが、実際の引用図書を借りてきてまで解説している記事はこのブログだけだと思います(笑)
『論文の書き方』清水幾太郎著:
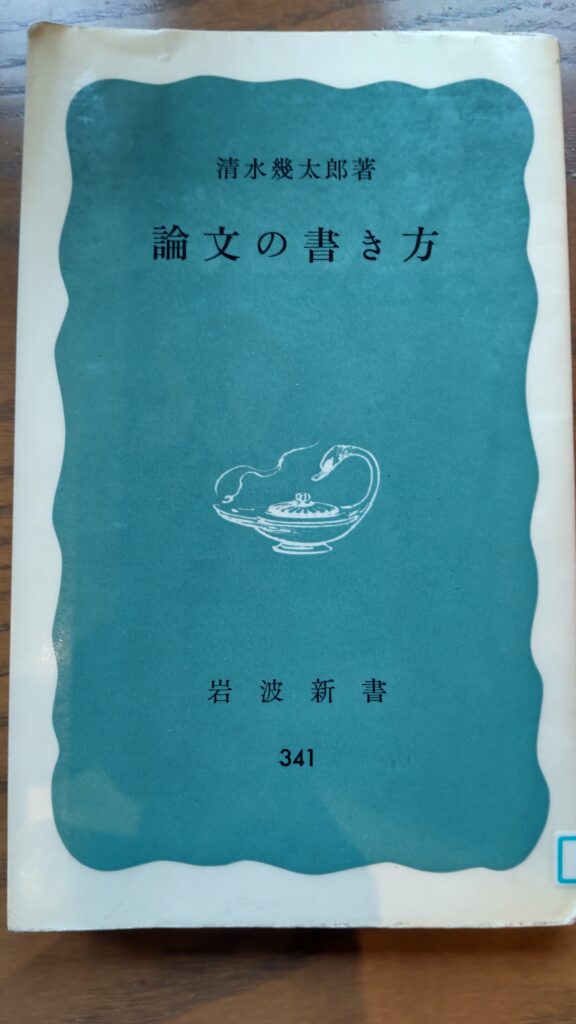
この本の初版はいつだと思います?
なんと、1959年!!今から約60年前に発行された図書です!
行政書士試験センターの問題作成委員の皆さん、結構古い本選んできましたね(笑)
ただ、少なくとも38刷発行されているので、名著と認識されていると思います。
令和3年度問58の引用箇所は?
この本(論文の書き方 清水幾太郎著)は、全部で214ページあるのですが、令和3年度行政書士試験 問58に引用されたページは、p54, 55のたったの2ページだけになります。
文章理解の問題に著者の意図を考える必要があるのか?
引用箇所/総ページは、2ページ/214ページ≒1%
本の1%読んだだけで著者の意図が分かると思いますか?
分かるはずないですよね…。
だから、『著者の考えを予想しなければならない』とか、適当なことを言っている人には注意してください。
では、文章理解の問題をどうやって解くか?
過去記事(①・②)でも紹介しましたが、最低限のテクニックは意識しておきましょう。
今日紹介するテクニックは、『キーワードの連続性』です!
以下の会話を見比べてください:
①『野球とサッカーだったら、自分はサッカーの方が好きだ。』『だって、野球ってピッチャー以外はあまり動いてないけど、サッカーは全員が動いているから。』
②『野球とサッカーだったら、自分はサッカーの方が好きだ。』『だって、テニスのサーブの初速って200km/h超えるんだぜ!超エキサイティングだよね。』
はい、②は超違和感あると思います。
野球とサッカーの話をしているのに、急にテニスの話をしています。
普通はこんな会話しませんよね。
当たり前のことを当たり前にやろう
何当たり前のことをコイツは言っているだ?と思った皆さん、
とりあえず令和3年問58に戻りましょう。
〜多くの具体的関係がそこから成長し分化して行く母体である。『・・・』人間の精神が現実に強く現実へ踏み込んで、その力で現実を成長させ、分化させるのある。
論文の書き方 清水幾太郎著
『・・・』に入る選択肢を以下から選んで見てください。
ア.しかし、この成長や分化は自然に行われるものではない
イ.精神が多くのエネルギーを放出し、強く緊張しなければならぬ
ウ.しかし、「が」をやめて、次のように表現してみたら、どうであろう
エ.「が」は無規定的直接性をそのまま表現するのに適している言葉である
オ.最初の実感としては、それぞれ二つの事実が一度に眼前や心中に現われるに違いない
・
・
・
・
・
・
どうでしょうか?
正解は『ア』になります。
正解だった人も不正解だった人も『キーワードの連続性』のテクニック使いました?
そうなんです。『・・・』の前後に”分化”というキーワードがあるので、”分化”というキーワードが入っている”ア”の選択肢を選べば正解に辿り着けます。
そして、②で説明したテクニック:接続詞も確認すると、『・・・』の前は”〜である。”という肯定の表現で終わっており、選択肢アは”しかし”で始まって”〜ではない”で終わっているので、逆接の接続詞である”しかし”も上手くハマります!!!
文章理解の問題が苦手な皆さんへ
どうだったでしょうか?
行政書士試験に出題される文章理解の問題は、表現が難しく難解に感じるかもしれません。
ところが、普段日本語を書いたり喋ったりするときに使う当たり前のルール(テクニック)を使えば、ちゃんと問題は解けます!!
当たり前のことを当たり前のようにやる!
を意識して問題演習してみてください。
文章理解が苦手な人は早めに練習しておきましょうね
いっくん@issay_univ
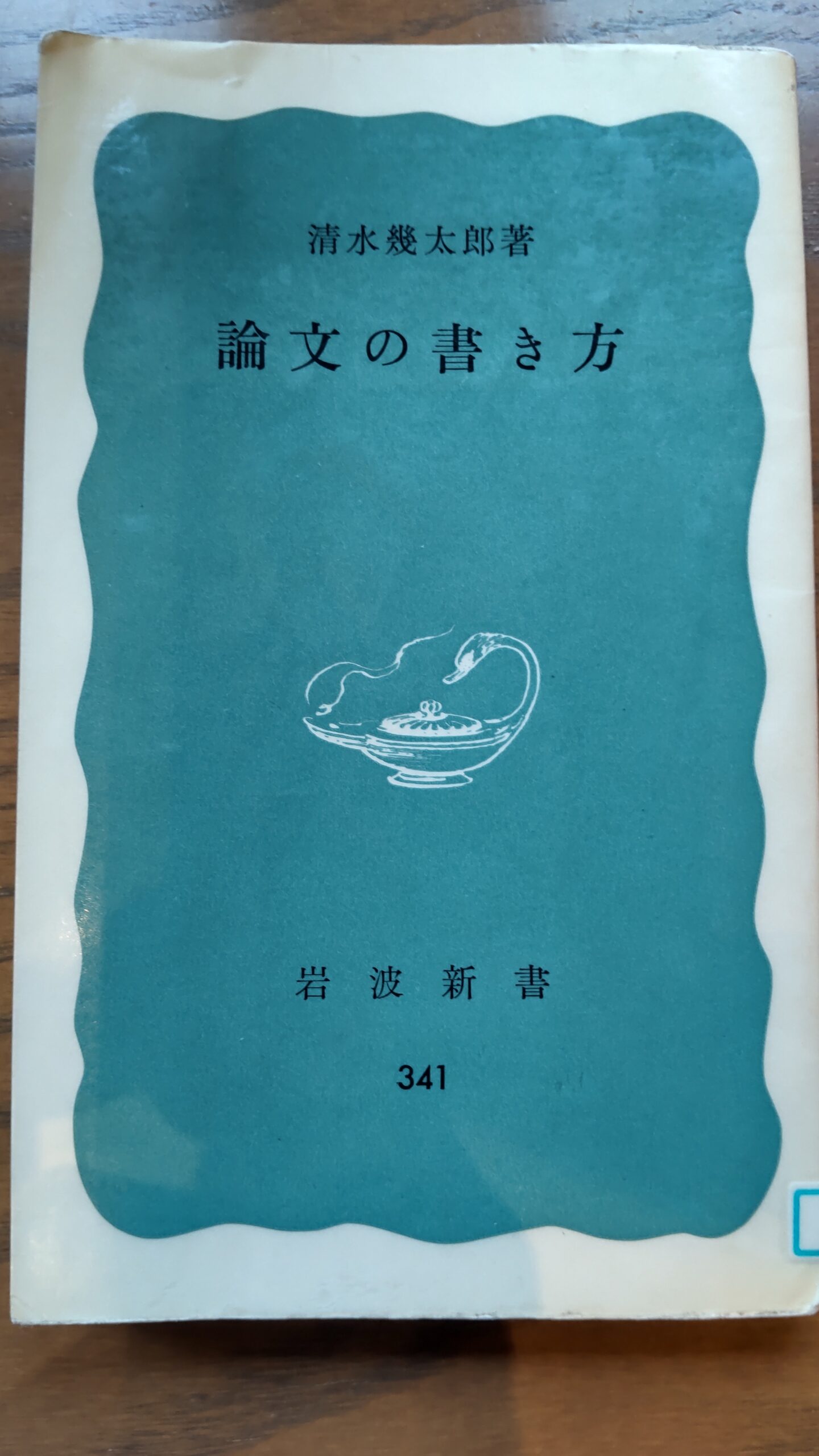


コメント